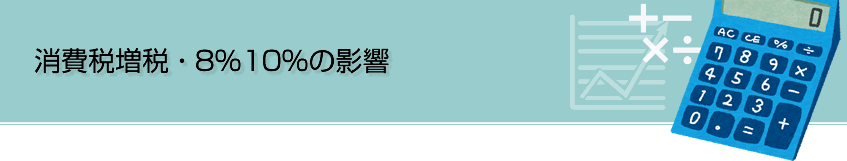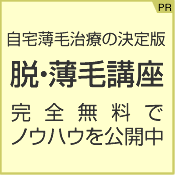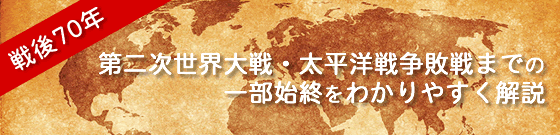消費税増税10%はいつから? 延期後の増税時期、衆議院解散の判断時期について解説 消費税増税10%はいつから? 延期後の増税時期、衆議院解散の判断時期について解説

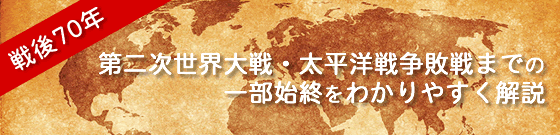
消費税10%の増税時期は当初、以下の日程により行われることになっていました。
しかし、ここへ来て景気の低迷の影響で、10%への増税を1年半延期するとの政府の方針が固まっていますので、10%への増税時期は以下のようになりそうです。
また、この10%への増税時期の延期については、延期と同時に「景気条項」の付則を削除するという方向で調整が進んでいるようです。
削除の理由は、増税の先延ばしを何度も繰り返すことでの信用低下による国債暴落等の懸念を回避するため、とのことです。
ですので、この「1年半の延期」が決定すると、景気動向の如何に関わらず、消費税率は平成29年(2017年)4月1日以降は10%ということになりそうです。
また、増税延期と合わせて衆議院の解散を決定する時期は、7〜9月のGDP速報値が発表される11月17日(月)の翌日18日(火)あたりではないかといわれています。
衆議院解散の理由は、消費税の10%増税を1年半延期することで、現在の衆議院の任期中に増税が行われなくなってしまい、安倍政権の最大の政策課題である経済政策「アベノミクス=デフレからの脱去」が中途半端な時期に終わってしまいかねないから、というもののようです。
つまり、消費税10%増税の経済への悪影響を、次の政権に処理させるのではなく、安倍政権で責任を持ってやろうということのようですが、単に政権の延命策であるともとれます。
以下は8%増税後の景気動向です。
4〜6月期のGDPベースでは、当初政府の予想は4〜5%の減少を見込んでいましたが、実際の現象は6.8%となってしまいました。
これにつき、民間エコノミストの多くは、政府の読みが甘かったと見ているむきが多いようです。
ちなみに、主要企業の4月の反動減は以下のようになっています。
| トヨタ |
△18% |
| ホンダ |
△12% |
| 三越伊勢丹 |
△8% |
| セブンイレブン |
前年同月を上回る |
| ビックカメラ |
△1割 |
| ケーズHD |
△2割 |
| すき家 |
△1% |
| ロイヤルホスト |
+8% |
| JT |
△45〜50% |
| 東京ディズニーランド・シー |
入場者数過去最高 |
【消費税10%への増税について首相および閣僚発言】
◆2014年(平成26年)8月18日/谷垣法務相 派閥の研修会にて
「来年は、消費税が(10%に)いける形を作っていく。その決断をしていくということが大事なのではないか」
「8%から10%に持っていけない状況になると、アベノミクスが成功しなかったとみられる可能性がある」
「既定の方針で頑張っていただきたい」
◆2014年(平成26年)6月20日/甘利経済再生相 月例経済報告にて
4月の8%への増税以後の個人消費について「引き続き弱めとなっているが、一部に持ち直しの動きもみられる」と、4月に引き下げた景気全体の基調判断を上方修正。
5月時点で見られた駆け込み需要の反動減の幅が縮小しているとの数値を示した。
◆2014年(平成26年)4月6日/甘利経済再生相 NHK番組内にて
「日本ではこれほど短期間に2回税率を引き上げたことはない。(10%への増税の判断は)そう簡単ではない」との見方を示した。
また、同日、記者団の取材に対して「総理が各種指標を精査して、(10%への引き上げは)8%への引き上げ時よりも慎重に判断される」と語った。
◆2014年(平成26年)3月18日/谷垣法務相 BS日テレ番組内にて
「一度決めたものをできるだけきちっと持っていくことは大事だ」との見解を示し、10%への増税はすべきとの意見を述べる。
◆2014年(平成26年)1月19日/安倍首相 NHK番組内にて
「4月に消費税率が8%に引き上げられますが、今の景気回復の流れを止めては元も子もないことです」
「経済成長ができなければ財政再建できません。7月〜9月の数字を吟味しながら総合的に判断していきたいと思っています」
「決断自体は今年中にしたい。その段階で来年10月から引き上げるか判断したいと考えている」
「企業の収益増が賃上げにつながるように努めていかなければいけません。多くの企業がベアを含めて賃上げをしていただけると期待しています」
◆2014年(平成26年)1月12日/甘利経済再生相 NHK番組内にて
「今年12月に判断できるのがベスト。その時には経済指標を慎重にはかる。7〜9月の数字が(増税時の駆け込み需要からの)反動減をどれくらいリカバーできているかが問題だ。日本経済の地力が回復しているのかどうか。それを広範な経済指標で見ることが必要だと思っている」
「8%に引き上げるときも首相は慎重な判断をされた。景気が失速しては元も子もないのは当然のこと。10%に上げるときは(首相は)より慎重な判断をされると思う」
「経済指標も大事だし、今回の補正で反動減をどう埋め戻すか。強力な成長軌道に乗せていくか。そういう施策も重要になるだろう」
「今回の経済対策の効果が出たかどうか。出ないとしたらどこに問題があったか。そこはしっかり検証する必要がある」
◆2014年(平成26年)1月6日/麻生財務相 財務省職員への年頭あいさつにて
「日本経済がうまく順調に伸びているかどうか、今年4~6月期、7~9月期の(経済成長の)結果がすべてを決める」
「(社会保障と税の一体改革については)5%の引き上げを前提に作られている。そこに到達しなければ、本来の目的は達成できない」
|
ただし、消費税8%への税率引上げが行われた後には、ほぼ間違いなく個人消費が落ちこみ景気が失速します。その景気の失速の度合いのどこまでが政府の許容範囲なのかということも気掛かりです。
これについては5.5兆円の投入が決定している経済対策の使途が適切かどうかにかかっていると言えそうです。
また、政府は企業に賃金を上げるように要求していますが、企業の側が今後どのようにその賃上げ要求に応えるのかにもよるでしょう。
それから、軽減税率の導入も、自民党はあまり前向きではないようです。
軽減税率の導入については連立与党の公明党が導入に前向きのようですが、自民党が押し切る形になるのでしょうか?それとも、部分的に導入する形になるのでしょうか?
そのあたりについても注目が集まっています。
ただ、これについては、たしかに、低所得者への配慮ということを考えると、食品などの品目に限定して軽減税率を設けるという方法だけではなく、税額控除や給付金など、いろいろな方法があると思いますので、ぜひ有意義な議論を重ねて決断してもらいたいものです。
具体的な課税時期について
それでは、もっと具体的に、事業を行う方々がいつから8%(10%)の消費税率で取引きすれば良いのかを見て行きましょう。
「課税売上」については以下の日が上記の日以降の取引きには8%(10%)の課税が必要になります。
| 資産の譲渡 |
資産の引渡し日 |
| 資産の貸付け |
契約や慣習による
売上げの支払を受けるべき日 |
| 役務の提供 |
目的物引渡しがある場合は、その引渡し日
目的物引渡しがない場合は、その役務提供が完了する日
|
「課税仕入れ」については「課税仕入れを行った日」が上記の施行日以降に8%、10%の課税がされることになります。(取引先が売上げを計上する日ともいえます)
<具体例1・商品の販売の場合>
2014年(平成26年)の3月31日に販売契約を結び、4月1日にその商品を取引先に引渡した場合には、原則的に消費税は8%が適用されることになります。仮に、契約時(3月31日)に代金を受領する場合にも同様に8%が適用されます。(経過措置による場合を除く)
<具体例2・修繕費の受け取りの場合>
2014年(平成26年)の3月中に車両の修繕を請負い、4月に代金を回収するとともにその車両を引渡した場合には、税率は8%が適用されます。仮に、3月次点で代金を回収していたり、3月中にその修繕作業が終わっている場合でも同様に8%の税率が適用されます。(経過措置による場合を除く)
概ね以上のようになります。
消費税率引き上げの経緯
それでは、この消費税増税の議論はいつから始まったのでしょうか?
その経緯をざっとまとめてみたいと思います。
まず、平成21年度に、「所得税法等の一部を改正する法律」の附則により、「消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成23年度までに必要な法制上の措置を講ずる」とされました。
その後、消費税増税に反対していた民主党が自民公明両党から政権の座を奪い、「政権交代」に成功しましたが、民主党三人目の首相に野田氏が選ばれ、野田政権が発足すると同時に「社会保障の安定財源の確保」などを理由に消費税増税に方針を転換しました。
ただし、民主党政権時にはいわゆる「ねじれ国会」の状態にあったため法案が成立するに至らず、衆議院の審議前に自民・公明・民主の三党により協議が行われ、平成24年6月15日に、消費税の税率引き上げ等が合意に達しました。(三党合意)
そして、平成24年12月の衆院選に自民党が圧勝し第二次安倍政権が発足、さらに平成25年7月の参院選で自民党が圧勝したことにより「ねじれ国会」が解消、同年10月1日に安倍首相により消費税を上記日程で増税する旨が正式に決定したという経緯になります。
いつから3%、いつから5%?
最後に、それ以前の消費税の歴史を振り返ると以下のようになっています。
1988年(昭和63年)
竹下内閣時に、消費税法が成立し12月30日に公布される
1989年(平成元年)4月1日
消費税法が施行され税率3%課税が始まる
1997年(平成9年)4月1日
村山内閣で内定していた消費税率5%への引き上げ(内訳は、国税4%+地方消費税1%)を橋本内閣が実施する(名目は「福祉の充実」)
2003年(平成15年)
消費税課税業者の免税点の基準額が、課税売上3000万円から1000万円にまで引き下げられる
2004年(平成16年)
価格表示の「税込表示」が義務づけられる
【関連ページ】
◆ 消費税増税後の表示方法は?
◆ 消費税増税と契約(施行日をまたぐ場合)の注意点は?
◆ 消費税転嫁円滑化法とは?
◆ 見積書作成の注意点は?
◆ 消費税増税の家賃への影響は?
◆ 増税のお知らせ・例文
|