|

 消費税10%で軽減税率は? 対象品目は? 逆進性とは? 消費税10%で軽減税率は? 対象品目は? 逆進性とは?

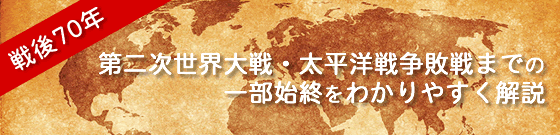
■消費税10%増税で、軽減税率は導入されるのか?
消費税率の引き上げで、「軽減税率」の導入の是非に注目が集まっています。
軽減税率の導入は、平成26年11月現在、まだ決定していませんが、8%から10%への増税の延期が検討されており、その過程で、景気後退への配慮などから軽減税率の導入の可能性が高まってきているようです。
もともと与党のうち公明党が軽減税率の導入に積極的で、自民党には慎重論がありました。
ですが、景気の後退が予想以上に進んでしまったこともあり、自民党内にも軽減税率導入の声が聞かれるようになったということのようです。
■軽減税率とは
「軽減税率」とは、特定の「対象品目」に対してのみ特別に消費税率を下げたり、消費税を免除したりする措置のことを言います。
軽減税率の対象品目としては、主に食料品や日用雑貨類などの「生活必需品」です。
海外では20%程度の消費税率の国はざらにありますが、そのような国ではだいたい軽減税率を採用することで、主に家計への負担を軽くしているのです。
そうすることで、低所得者の負担を減らし、高所得者から大く税金を徴収するということを主眼として軽減税率という制度が導入されているわけです。
ただ、高所得者であっても生活必需品は必要ですので、軽減税率を導入しても、低所得者の負担を軽減出来ないという考え方も存在します。
以下、その辺りについて解説しましょう。
■軽減税率の問題点と代替案
「逆進性(ぎゃくしんせい)」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「逆進性」とは、「累進性」という言葉の反意語です。
「累進性」というのは、高所得者、いわゆるお金持ちから多く税金を徴収するという性質のことをいいます。
「逆進性」はその「累進性」逆ですので、低所得者から多くの税金を徴収するということになりますが、大雑把に言いますと、概ね、消費税がこの「逆進性」を持つものであると主張する党派と、「逆進性」はないものとする党派や評論家との間で議論されているのがこの「消費税の軽減税率」の導入の問題点ということになります。
具体的に説明しますと、総収入のうちに占める「生活必需品にかかる費用」は、必然的に低所得者ほど高くなる傾向にあると主張するのが「逆進性あり」とする人々の主張です。
そのため、生活必需品にも他の品目に適用される税率と同じ税率を適用すると、当然、高所得者よりも低所得者のほうが負担率が高くなる、という現象が起きてしまうというわけです。
しかし、「逆進性なし」とする人々の意見はこうです。
低所得者は安価な生活必需品を購入し、高所得者は高価な生活必需品を購入する傾向にあることから、消費税の負担額は必然的に高所得者の方が高額にのぼるのであり、その状況下で生活必需品に軽減税率を適用すると、逆に高所得者の負担を多く軽減してしまうことになりかねない、というものです。
また、その他にも、軽減税率を導入することで税収が減ってしまうことにより増税の意味を成さなくなる(増収できなくなる)という意見や、軽減税率ではなく収入の額に応じた「税額控除」などで対応すべきだという意見など、様々な意見が出ており、審議に時間がかかっている模様です。
ちなみに、世界各国では特定の食料品などの税率をゼロにするなどの措置がとられていますが、そもそもの税率が、例えばヨーロッパ諸国では20%前後という高税率ですので一概に比べることも出来ません。
→詳しくはこちら「世界各国の消費税率と軽減税率について」
この議論は、まだしばらく続きそうですので、進展がありましたら当サイトでも続報したいと思います。
【関連ページ】
◆ 消費税増税の家計に与える影響は?
◆ 消費税増税の企業・会社に与える影響は?
◆ 世界各国の消費税率と軽減税率について
|
| (C) 消費税増税8% 10% |
|